患者の声と対話型ADRというシンポジウムが
早稲田大学で開催されたので傍聴してきた。
実に内容が濃く、かつ頭の中がクリアになるものだったので
記憶が鮮明なうちにご報告したい。
ちなみにNHKのカメラも入っていたようだった。

会場は早稲田大学の南門を出てすぐのところにあるという
小野記念講堂。
小雨の中、地下鉄早稲田の駅を出て歩いていくと
商店街は、野球部の全国優勝を祝う張り紙ばかり。
あれも早稲田で、これも早稲田、大したもんだ、と思う。
着いてみると楽屋まで完備の実に立派なホールだった。
前置きはこれくらいにして早速報告を始めよう。
まず和田仁孝早稲田大学紛争交渉研究所長が挨拶。
「被害者や遺族が参加する新しいタイプのADRをめざす。しかし、どんなに善意に考えたとしても、我々は専門家でしかなく、本当に被害者や遺族の声に答えることにはならない。いろいろな機会で被害者や遺族の声を聴く必要があるだろうということで、今回はここに焦点を当てて2人の遺族の方にお話をいただく。それを受けて我々のNPOがどう考えているのか説明し、さらにパネルディスカッションで議論したい。最後には国会議員も交えてさらに論議を深めたい」
いつものことながら、分かりやすいアジェンダだ。
今からの2人の話を克明に記録することが肝要だなと合点する。
=====
最初の佐々木孝子さんは
1994年1月に二男の正人さん(当時17歳)が
バイクの自損事故で救急病院に搬送されたのだが
十二指腸破裂を見逃された挙句、MRSAの院内感染によって
事故後15日目に亡くなったという経験の方。
聴けば聴くほど理不尽極まりないと思うのだが
感情を高ぶらせることなく低い声でゆっくり噛みしめるように話す。
「もう13年前になりますが、三人兄弟の真ん中の子供を医療事故で亡くした。医療者に対して私は高級職、専門職として信頼と尊敬の念を持っているが、その時にことについては納得がいかなかった。バイクの自損事故で運び込まれた救急病院で、非常な腹部の痛みを訴えていたにも関わらず単なる打撲と診断され、食事に普通にさせていた。9日目に造影検査をして初めて1.5センチの亀裂が見つかった。あまりに遅い診断だったし、それから行った長い手術の後、『食べさせたのが悪かった。食塩水で洗った』と言って、その晩は出てこなかった。翌朝になったら黄疸の症状が出ているので訴えたら『ここでは処置する設備がない。お母さんあらめてください』と。そんなことを言われてあきらめる親がいるはずがない。慌てて済生会へ転院させようとしたら、その時になって『もう一度手術させてほしい』と言ってきた。転院させたのだけれど、2日目にMRSAの感染が分かって、正人がお母さんもうダメと指でバッテンを作った。葬儀の後で、先生いったいどうなってたのですかと尋ねたら、分厚い文献を持ってきて、これにも載ってないので分からなかったと言われた。しかし、どうしても納得いかなかったので提訴することにした。医者を訴えるのはよほどのこと。
それなのに途中から弁護士が示談しましょう、と。1年ぐらい準備書面を交わしていて、『争点になる事実がないか』と言うから、いろいろ調べて救急の腹部外傷に関して鑑定してくれる医師が沖縄にいたので行ってみたら、レントゲンの中に教科書に出せるくらい十二指腸破裂に典型的な気腫像が見える、と。これを分からない医者が救急病院にいるのか、と。それで、その旨を準備書面で出したら、相手からは『最初からわかっていたけれど、あなたが主張しないので言わなかっただけだ』という不可解な答弁書が出てきた。しかも弁護士から、『もう準備書面を書けないし、先にも進めることができない』と言われ、和解を勧められた。最初から和解する気なんでなかったので弁護士を解任して、どうしようかと思っていたところで本屋さんで和田先生の書いた本人訴訟に関する論文を見つけて、本人訴訟で行こうと決めた。裁判長からは威圧的に『せっかく和解が見えて8合目まで行っていたのに3合目まで戻ってしまった。弁護士を決めなさい』と言われたが本人訴訟で行くと突っぱねた。
(裁判官も代わって)ようやく医師の証人尋問をできることになったのだが、出廷してきた医師2人の顔を見てハッとした。2人ともでっぷりとした体格だったのに、顔が半分くらいスリムになっていた。心が痛んだ。医師は私の顔を見ることもなく謝罪の言葉を述べることもなく、私の問いかけには無言だった。私は遺族は一生癒されないのだと伝えたかった。
裁判は精神的に張り詰めた状態が長く続く。しかも相手側からは真実のない書面が出てくる。多くの被害者・遺族は、まず診療期間中に何があったのか知りたいと思っていて医者から聞きたいと思っているのに答えてくれない状況があると、それだったら公の訴訟という場に呼び出してもらおうという気になってしまう。しかし医療過誤が裁判に向いているかというと必ずしもそうでないと思う。
ADRのシステムは5年前に知った。ミスがあった時に医療者が説明し真摯に謝罪することによって、医療者は次の医療へと向かっていけるし、遺族も立ち直れると思う。そうすればマスコミにセンセーショナルに取り上げられることもなく、解決の道筋が開ける。
訴訟の後、北海道から九州までいろいろなところから電話がかかってくるようになった。多くの人が医療者への不満を漏らす。それをカウンセリングのように聴いてあげる。長い人だと1時間以上話す。ただ聴いてあげるだけでも、最後には少し気が楽になりました、ありがとうと言って皆さん電話を切る。
13年も経っているが昨日の如く息子のことを思い出す。当時88歳だった父が『誰にも迷惑をかけることなく逝ったんだから、あきらめなさい』と言ってくれた。その父も3年前に97歳で亡くなった。100年近く生きたとしても人は必ず死ぬ。息子の人生はたった17年だったけれど、その分凝縮して生きたんだと思うことにした。裁判の途中で病気になって1週間入院した。それが息子からの「自分の人生も大切にしなよ」というメッセージのように受け止められて、それからは前向きに楽しく毎日を過ごしていこうと思えるようになった。
医療者の使命感を尊敬している。どうか心やさしいケアをお願いしたい」
=====
この医療事故は民事の一審で佐々木さんが勝訴した後
医師2人が控訴し
「反省してない」と考えた佐々木さんが刑事告発して
最終的に業務上過失致死で医師2人の有罪が確定し
2人の医師は罰金刑とさらに業務停止3か月の行政処分を受けた。
民事訴訟も医師側が控訴を取り下げる形で和解が成立したという。
なかなか言葉を発しづらい雰囲気の中、和田所長が
「分かると言ったら失礼になる。でも学んでいきたい」
と引き取って、次の村上博子さんの紹介へ移った。
最後まで事情がよく分からないままだったが
話をつぎはぎすると、どうやらこういうことらしい。
神奈川県の大学3年生だった息子さんが心拡大によって亡くなった。
実は大学が行っていた定期健康診断では
心拡大は判明したいたのだが本人にその結果が知らされていなかった。
村上さんは和田所長がインタビューする形式で話をした。
和田
「息子さんが亡くなって、まず何をしたいと思ったか」
村上
「何が起きたのか事実を知りたいと思った。私にとって息子の死は理不尽なあってはならないことに思えた、二度と息子のようなことが起きないようにしてほしいと思った」
和田
「まず裁判するつもりがないと宣言したというのが珍しい」
村上
「最初からそうだったわけではない。パッと思いつくのは裁判。とはいえ、裁判のことなど何も知らない。調べてみたら、何が起きたか知りたいとか、二度と同じことが繰り返されないようにとかいった自分の願いを叶えるものではない、そういう気がしてきた。お金も時間もかかるし、息子の死を損害として金銭換算しなければならないのが気持ちに馴染まない。だったら最初からやりませんと。それに裁判では死の決め方が狭い。この時こうしていれば死ななくて済んだというのは全部明らかにしたかった」
この時点では「死の決め方が狭い」という言葉の意味が
よく分からなかったのだが
後になって実に重大な意味を持っていたことに気づく。
=====
和田
「狭いとは」
村上
「健康診断の結果を息子に知らせてくれていれば治療できたかもしれない、といった具合に、資料開示をかけてみると、ここでもしもう少し医療者が突っ込んで対応してくれていれば、死なずに済んだかもしれないということがゴロゴロしている。それをすべて握りつぶされた。その過程を検討して改めるべきは改めてほしい。
健康診断が、大学にとっては就職証明書を作るためだけのものになっていて、医療者にとっても大したものが出てこないと決めつけられていたように感じる。息子の死をケーススタディに再発防止の検討をしてほしい。
そう思って、医療機関の最高責任者や現場レベルの責任者に都合5回面会を申し込んだけれど、残念ながら誰にもお目にかかることができなかった。こちらは開示されたものが真実なのか疑義を持っていて、とても事実にたどり着けないという感覚を持った。そういう対応をするのは責任問題を恐れているからだろうと考えたので、だったら上の人に面会して責任追及や裁判はしないと伝えて、事実を聴きたいと思った。しかしあっさり断られてしまった。
こちらは怒り狂って全て文書にしてぶつけてしまった。それでもやりとりの肝心のところは曖昧だし、改善案もおざなりに感じた。だったらと事実解明はあきらめて、再発防止の一点に絞ってと提案したけれど、それでも現場の責任者からは『説明を尽くした』という文書での回答しか来なかった」
これまた凄まじい話である。
例えるなら、丸腰で「話せば分かる」と近づいているのに
相手が銃を構えたまま砦から出てこないということだ。
たぶん、こんな事例が少なくないのだろう。
村上
「患者がまだ質問があると言っているのに、説明は尽くしたという医者がいるのか、と怒り狂った。医療者の良心に訴えていけば何とかなるのでないかという信頼が音を立てて崩れた」
和田
「医療者の一人ひとりと話してみると、良心を持っているし、悩んでもいることが多い」
村上
「しかし、その部分が何にも出てこなかった。医療者も苦しんでいるんだと感じ取れていたら、状況がまた変わったかもしれない」
和田
「文書でやりとりしたのが問題だろうか」
村上
「窓口が総務の部署で、医療者とは一度も話すことができなかった」
=====
和田
「話をできていたら、納得いく対応が得られたと思うか」
村上
「まず、きちんと話を聴いてほしい。納得いくまで説明をして、そのうえで私の言い分を聴いて欲しかった。事案解明した説明と反省や後悔、あるいは力及びませんでという言葉と息子のようなことを二度と起こしませんという誓いの言葉があれば、納得できたのでないかと想像する。
会っても文書と全く同じ対応だったら怒り狂って何も言えなくなってしまうかもしれない。単なる謝罪だけなら受け入れられない。
会うのはいいことで解決する手段かもしれないけれど、お互いに準備をしてからでないと意味がないのでないかと想像する」
和田
「どういう準備?」
村上
「疑義を申し立てるのはよほどのこと。スーパーのレジ打ち間違えとは訳が違う。迷いに迷った挙句の行動なので、感情的に崖っぷち、ギリギリの所に立っている。マイナスの感情だけで、しかも自分自身を責める気持ちも根底にある。そんな状態だから、感情そのものをぶつけてしまいがちだし、自分が何を望んでいるのかすら分からなくなる。
医療者と会う前に、そういったマイナスの感情を脱ぎ捨てないと、脱ぎ捨てるのは無理だとしたら、せめて抑え込まないと。被害者が加害者と話をする図式ではうまくいかない」
和田
「村上さんに『被害者』という言葉に違和感があると言われた。マイナスの感情を抑え込むことができたという意味では自分自身でメディエーションをこなしているのだろうか」
村上
「私には、まじめに話を聴いて、しかも批判してくれる家族や友人がいた。その点で恵まれていた。周りに医者がいたのでカルテを読んでもらったし、弁護士の友達もいた。そうした人たちに支えられることで、自分の中でキリの良いところで終わらせることができた」
和田
「医療者側も準備しなければいけないだろうか」
村上
「鎧を脱いでもらいたい。組織、保身、体面、世の中を渡っていく鎧を脱いで、良心だけで対峙して将来への誓いを立ててほしい。自分には、できないと思ったら、それも口に出してほしい。組織も、大きな度量で医療者にそれを許してほしい」
和田
「医療機関との交渉では得るところがなかったけれど、文部科学省が対応してくれたとか」
村上
「いろいろと文書にまとめて大学へ送った最初の項目が、健康診断結果の通知方法についてだった。大学の方法は明らかに問題があったけれど、調べてみると全国の多くの大学で同じ方法を取っていた。そこで文部科学大臣に手紙を出した。お役所だから期待していなかったのだけれど、「どういう結果であろうとも本人へ伝えるよう」全国の大学へ文書を発したとのお返事が来た。
たったひとつだけれど願いが叶ったと思うことにした。息子の死が価値あるものになるのは遺族にとって大きな意味がある。
私が伝えたかったのは、疑義を申し立てた人の気持ち。医療者には理解してもらえなかった。危険人物のように見なされ、相手は隙を見せないように身構えている。大きな溝を感じた。その構図では気持ちが伝わるはずがない。
医療者へ申し上げたい。疑義申し立てした人を固定観念で見ないでほしい。真っ正面で受け止めてほしい。それが問題解決につながる」
=====
まさに圧巻の意見陳述である。
ここから議論がどう展開していったのかは稿を改めることにする。
今日になって遅まきながら気づいたこと。
遺族も一生恨みや怒りを抱えていくのは耐えきれないことで
どこかで心に区切りをつけたいと願うものなのだろう。
ところが医療者が出てこないことによって
いつまでも宙ぶらりの不幸な状態に留め置かれるわけだ。
これは二重の苦しみでないか。
やはり医療者が出ていける場を作らないといけない。
シンポジウムの報告に戻ろう。
村上博子さんの話を受けて和田仁孝所長が
中村芳彦弁護士(法政大教授)を紹介しつつ
「これから設立するNPOは、誰かが誰かのためにではなく、皆で皆のためにでなければ機能しないと考えているので、ぜひ参加してください。使ってください」と呼びかける。
中村
「気持の問題を解決することが問題の解決につながるということが印象的だった。また裁判が果たして有効なのかという問いかけもいただいたと思う。では、どういう風に対応したら良いのだろうか、ということで私たちはNPO法人の『医療紛争処理機構』を設立する」。
と、資料を交えて説明しだす。
ロハス・メディカル6月号の「ストップ!!医療崩壊2」の
4見開き目と重複するので資料は採録しない。
「これまでも裁判の対立構造によって不信を増幅し医療崩壊を進めてしまってきた。溝を埋めるには対立構造では不可能。医療は強い信頼関係の中で行われるもの。医療ADRの一つの試みとして、こういう仕組みを考えた。NPOの認証を受け、さらにADR法の認証を受けなければならないので、実際にADRが稼働するのは来年はじめくらいだろう。それまではメディエーターの育成支援が主な業務になる。閉じた機関ではなく、様々な方の参加を得て考え直す場、信頼関係構築の場としたい」
と急ぎ足で宣言して休憩に入った。
=====
休憩の後はパネルディスカッション。
向かって左から和田、佐々木、村上、中村と来て
その次が土屋了介・国立がんセンター中央病院院長
さらに黒岩祐次・フジテレビ解説委員(昨日の写真参照)。
新たに加わった2人がここまでの感想を話すところから再開。
黒岩
「お二人の話を伺って、その心の痛み、母親の思いはすごいなと感じた。死を再発防止につなげるとか、真相解明するというのに裁判が向いていないというのも説得力があった。10年ほど前にフロリダの病院を取材に訪れたときのことを思い出した~」。黒岩氏が紹介したマーティン・メモリアル医療センターの件はご存じの方も多いと思うので割愛する。
土屋
「黒岩さんが指摘した欧米と日本の対応の違いは、思想の違いの現れでもある。欧米では事故をゼロにするのは難しいと捉えているので起きた後の対応を常に考えている。日本は間違えたヤツを罰して、そうすれば事故がゼロになるだろうと考えている。
佐々木さんのお話は、医療者としても当該医師の態度や誠意には問題があると感じた。
村上さんのお話は事情がよく分からないのだが、医療者に疑義を申し立てる際にマイナスの感情でパンパンになるまで我慢してからぶつけるという話があった。医療者からすると、だから困るとも言える。もっと早く言ってもらえればいいのにと思う。退院する時になって病室が暑くて苦痛だったというようなことを言う人もいるのだが、入院中に言ってもらわなければ、応えようがない。それから責任者に交渉しようとしたということについては、私の病院でも何でもかんでも『院長を出せ』という人が多いのだけれど、そういうのでいちいち院長が出て行っていたら病院が回らなくなってしまう。多くの病院で医療事故対応のトップは副院長。私も4年間務めて、いろいろな場に出て行った。医療者がなぜ面談を嫌がるかというと、それこそパンパンに不満が溜まっているので、たいてい2時間は話を聞かなければならない。あまりに副院長の業務が多いので、院長が部長にも振るようにと言ってやらせたことがあったけれど二度やって二度とも結局私のところまで回ってきた。部長連中が悪いのは、まだ相手が話しているのに途中で遮って、相手の言ったことを医学的に解説しようとした。だから、私が黙って聴けと言ったら『ほら見ろ、副院長先生は聴いてくれるじゃないか』と言われた。要するに医者と言うのは人の話を聴くトレーニングができていない。
いずれにせよお二人の話を聴いて自分の施設の教育をし直さないといけないと痛感した。素直に皆様の声に耳を傾けることが改善の第一歩なのだろう」
和田
「パンパンになる前に早く言ってほしいという医療者側からの意見があった。一方でそうはいっても相手は医者でイーブンではないのでないか。対話するといっても、そんなに理想的にはいかないのではないかという批判をよく受けるのだけれど、患者側としてはどう受け取るか」
佐々木
「対話は大切。顔と顔が合うから心も通じ合う。絶対に必要」
村上
「医療者側に聴いてほしい。火中のクリを拾ってほしい。たとえば待ち時間が長いというクレームがあったとしても、本当は診療に不満があるのかもしれない。なぜなら、おいしいラーメン屋さんに行列しても誰も文句を言わない。言葉の向こうにあるものをほじくり出してほしい。クレームの中に解決すべき課題があると認識してほしい」
=====
和田
「医療機関側が聴く姿勢を持っていればよいが、そうでない場合にそれをどう変えていくのか。現実にできるような体制を整えていくときに、まず中村さんにフェアネスをどう捉えればいいのか伺いたい、土屋先生には医療機関の体制をどうすればよいのか伺いたい、黒岩さんにはメディアとして敵対的でない構図をどう描くのか伺いたい」
中村
「まず院内での安全管理の徹底をすること。安全管理部門の人間は臨床現場と距離を取って、透明性・公平性のある運用をできるようなシステムを持っていることが必要だろう。しかし最初から期待すると、そもそもそれができないから問題になっているのであって、どうすればいいのかという話になってしまう。
少なくとも患者側に対するサポート体制は必要であろう。大きな情報格差が依然としてある。その意味で我々の描く院外ADRにはサポート機能も必須と考えている。患者側自身の理解と納得が実現されることを通じてフェアネスも達成される。
院外ADRに強制的調査権のないことを批判されることが多いのだが、証拠保全をかけてからADRに来ていただいても構わないわけで、その辺りはいきなり訴訟ではない柔軟な構造が取れる」
土屋
「根底に患者側が満足していないことがあるというのがポイント。日常診療からキッチリ対話をするように見直していかなければならないと思う。私は院長になってから、外来を完全予約制で1時間6人までにした。それまでは主治医がどんどん診察を入れて1時間に10人も20人を診るようになっていた。患者さんのためと本人たちは言うけれど、結果としてきちんと対話ができていなかった。そういう風に診療そのものから見直していかないといけない」
黒岩
「前提条件がキッチリできていないと難しいと思う。ミスがあった時に隠したくなるのが自然な反応で本能のようなもの。そのままの状態で対話しろと言ったって、逮捕されるかもしれないと思ったらムリ。米国では、件のベン君の事例をモデルにするにあたって、クリントン大統領が全部出しなさい、その代わりそれは刑事で問わないということをした。罪に問われないということが大前提。メディアの人間として、この問題に関しては内心忸怩たる思いがある。どの立場に立っているのか問わざるを得ない。特にテレビはエモーショナルに患者さんの立場に立った方がやりやすい。患者の声を伝え、一方で取材に応じない病院やドクターを敵として追及するというのはよくある。印象として善良でかわいそうな患者と殺人者に値する医療者という構図にしてしまう。福島県立大野病院事件があって、その後どうなったか。それでメディアはいいのか。この医療崩壊をどうやって食い止めるのかはメディアが抱えている課題だと思う」
=====
佐々木
「記者会見でよくテレビカメラに向かって病院側を謝らせてますよね。あれは一体誰に対して謝罪させているんですか。先に遺族に謝罪させるべきではありませんか」
土屋
「極論すれば会見しないでも良いと思う。被害者に直接謝るべき。でも、メディアに責め立てられ、メディアに用意されて出ていくというのが実際のところ」
村上
「土屋先生が先ほど責任者に話を持って行ったのが無謀だとおっしゃった。確かに自分でも無謀だったとは思うけれど、方法論としては間違ってなかったと思っている。というのが、最初に質問した際に現場の責任者からは明らかにおかしな回答が来た。これは組織としての意思決定があるに違いないと感じた。黒岩さんの紹介したベン君の件では、婦長が最高責任者に『これを検査したら病院になるかもしれないけれど調べるか』と尋ねて、最高責任者が了承している。そういうくだりがあったので、だからそのことを紹介した和田先生の本を手紙に同封して担当理事あてに『どうかこの本の付箋を付けた個所を読んで欲しい。あなたの英断が必要』と手紙を書いた。しかし結局決断はしていただけなかった。上の方の意思がないと、事実も出てこないし、医者も大変な思いをするのだと思う」
土屋
「組織として対応しないといけないのは確か。私が先ほど言ったのは、決まり文句のように『院長を出せ』という人が多いという話」
黒岩
「終末期医療なんかまさにそうだけれど、殺人罪と一線を画したところへ持ってきてあげないと。免責は大事な要素だと思う。
メディエーターというのが、話に聴いてもどうもイメージがつかめなかったのだけれど、実際に活躍している人に会ってなるほどと思った。医療福祉チャネルの番組で大阪・豊中病院の水沼さんというナースの仕事ぶりを追った。それこそマイナスの感情でパンパンになった人が突然やってくるわけだが、その方は奥さんがミスで寝たきりになってしまった。で暴れまわって大クレーマー。水沼さんに対しても、しょせんお前も病院から給料もらってる病院側の人間やろうと罵倒する。それに対して、たしかに私は病院側の人間ですけれど、きちんとやりますから、思う存分話してください、とまず不満を聴きとって、それを今度は現場の人間に対して、テクニックなのか少しキツイ位に『こんなことがあったのか』と問いただす。それを見て旦那さんも心を開いていくわけ。最初は大クレーマーだった人が私たちのインタビューに対して『水沼さんには感謝している』と言った。『裁判になった時も暴れたけれど納得した。こういう気持ちにならせてくれたことに対して感謝している』と。そういう人間力のあり人がメディエーターになるんだなと思った」
和田
「水沼さんクラスのメディエーターは今日の会場にも何人もいる。刑事免責の件だが、日本以外の国では医療事故は刑事事件にしない。それは遺族から見た時にどうなのか」
佐々木
「私の場合は刑事へ行って業務停止3カ月の行政処分も出た。でも聴いたら院長は業務停止中も毎日病院に来ていたらしい」
村上
「裁判をやっわけではないのだが、池田小事件で宅間死刑囚が『早く死刑にしてくれ』と言って執行されたのを見て、遺族は気持が治まるのかなと思った。言葉は悪いが、もっと本人に自分のした罪に苦しんでもらいたかったのでないかという気がする。医師の場合の刑事罰もそれで遺族の気持ちの整理がつくのかなとは思う。気持の整理がつくかどうかの方が大事。佐々木さんの例のように形だけの罰だったら余計に腹が立つ」
=====
和田
「医療者の苦しみが刑事罰だと遺族に伝わらないという話だが、それをつなぐのがメディエーションでありADR」
土屋
「解決した後も恨みは残ると思う。ただ、医療者が真摯に反省して改善があれば遺族の慰めにはなるだろう。ただし、対話の場には水沼さんのようにエクセレントなメディエーターでなくても、医学的な常識のズレを埋める翻訳者は必要だと思う」
ここでディスカッションの第一部が終わり中村、土屋の両氏が退席。
代わりに鴨下一郎衆院議員(自民党、医師)と
鈴木寛参院議員(民主党)が加わって第二部へ。
=====
鴨下
「ここまでどういう議論が行われてきたか承知していないが、対話型ADRを構築すべしというシンポジウムの趣旨については、まさにその通り。福島県立大野病院事件に大変ショックを受けた。政治も取り組まないといけない。厚生労働省も第三者委員会を作ろうと動き始めているので、その動きについてまずご報告したい。
本当は医療は安全・安心にかかれるものでなければならない。一方で医者は訴訟に対して防衛的になりがち。胸襟を開いて対話するためにも、いきなり警察・検察でない仕組みが必要」
鈴木
「行政監視委員会に所属して医療ミスがどうやったらなくなるかといった問題を考えてきた。また福島県立大野病院事件で鴨下先生ともご一緒に医療者の請願を川崎厚生労働大臣に取り次いだりした。
この問題は相当根が深いというか、いろいろなレベルで様々な問題を含んでいる。医療現場のコミュニケーションの問題でもあり、医療機関のガバナンスの問題でもあり、霞が関・永田町の医療政策の問題でもある。この問題こそ熟議・熟論が必要であり、今日だけで解決策が示せるはずもないがキックオフとしたい。
医療崩壊、保身医療、委縮医療がどんどん広がっていて、みな善意で関与していて、加害者はいないにも関わらず被害者がいろいろなところに出ているという状況だと思う。また霞が関の議論が、我々の意図とズレてきていることも指摘しておきたい」
和田
「鴨下先生からも言及のあった医療版事故調というか原因究明機関について、遺族としてどう評価するか」
佐々木
「対話型ADRのことで頭がいっぱいなのだけれど、第三者機関は行政任せになるような気がする。遺族は情報を得ることができないし、医療者の顔も見ることができないのでは? 被害者はその場の議論でどんな気持ちになるのだろう、納得できるのだろうか」
村上
「実はパブリックコメントを送った。書いたのは、死亡原因を広く取ってほしいということ。これからの医療を良くするためという観点に立って、行政とか保険点数の所まで遡って原因を広く取ってほしい、と。それから被害者・遺族の申し立てで調査に入ってほしいし、その結果を踏まえて対話の場を設けてほしい。そのうえで話し合ってほしいと書いた」
=====
鴨下
「第三者機関の議論は始まったばかり。こうした声は吸い上げなければならない。患者の疑問と医療者の言い分はすれ違いがち、何が重要か、罰することなのか、補償を受けることなのか、むしろ多くの方にとっては、なんでこうなっちゃったのか知りたいのだろう。当事者どうしで話してもらう。医療者は防衛的になりがちなので、お互い納得するものを見つける、患者が納得できる仕組みでないと意味がない」
ん?と思った。第三者機関の議論が既に取りまとめ段階に入っていることは耳に入っていないらしい。本題とずれるので、あまり深く考えないようにしておこう。
鈴木
「村上さんのおっしゃった死亡原因を広く取るというのは非常に大切なこと。というのは先ほどから対話が大切だという話になっているが、医師が患者さんと10倍コミュニケーションの時間をとったとしても診療報酬は変わらない。もっとヒドイ例で言うと家族とのコミュニケーションも大切だと思うのだけれど、それに対しては診療報酬は1点もつかない。そんな中、マジメな医療者たちは自己犠牲を払って患者や家族と対話しようとするのだけれど、やればやるほど燃え尽きてしまう。原因といった時の食い違い、それは直接の死因なのか、それともその死因を発生させてしまったシステムの問題なのか、きちっとしておく必要がある。たとえば日本外科学会の調査では、実に外科医の7割が当直明けの手術を経験しているという。つまりほとんど徹夜明けで手術している。そんな状態でミスをした時にそれは果して医療者本人の責任なのか。本人を追及しても恐らく再発防止にはならず、リスクのある医療行為をやらなくなるだけ。二度と繰り返さないために何が必要なのか、という原点に帰ってくることが大切だと思う」
和田
「だんだんマクロの話になっていくのだが、事故の当事者にとっては常にかけがえのないミクロの話。そういうミクロをすくい上げるのはメディアの得意分野なのかなという気もする」
黒岩
「ミクロを取り上げやすいのはその通りなのだが、エモーショナルに動かして大きなグランドデザインを壊すことになる危険性が常にある。死亡原因を広く取る、というのは実に素晴しい表現。対話にはテクニック性もあるのだが、医療者の教育で教えているのか、などなど言い始めるとキリがない。一つひとつやっていくしかないのかなと思う」
=====
和田
「そういう意味でも一つひとつの被害から学ぶ、こういった機会が重要だと思う。では折角の機会なので会場の方、質問があったら」
会場1
「大学で倫理学の研究者をしている。今日の話を聞いていると、これはもはや法律の世界ではなく倫理学の分野だと思う。倫理学的に言うと責任は応答可能性と翻訳するのだけれど、医療ADRでは誰が誰に応答するのか、主に医療者が患者・被害者に対するものと理解したが遺族・被害者に対して一般市民がどうレスポンスすべきとお考えか、レスポンスという言葉がなじまないとしたらどう下支えしたらよいのか」
和田
「個々の体験に互換性はないので、応答する際には医療者とか被害者肩書が抜け落ちて、最終的には個と個のレスポンスになるのだろう。もっとリテラシーというかレスポンスを高める活動はNPOとしても必要になるだろう」
村上
「パブリックコメントに、普通の人を入れてほしいと言った。普通の人の感覚を取り入れてほしい。医師や弁護士が持っているのは普通の人の感覚ではない」
黒岩
「普通の人というのが一番難しくて、実際に探そうとしても難しい。先ほどの一般の人のレスポンシビリティは、外から見ているのだと思う。あそこの医療機関は患者の声をよく聴いてくれるという評判が一般の人も巻き込んでいくのでないか」
鴨下
「事が起こってしまってからの話をしているが、倫理的には紛争を未然に防いだ方がよいに決まっている。情報応答性に欠ける医療現場では、どんどん不信感を増幅する。開業医が増えているのは、安全なところに逃げ込もうという医療者の心理があるので、リスクの高い行為をしている人へのサポートをしないと解決しない。医療ADRだけでなく総がかりで取り組まないと。そして、もっともっと広い意味で医療を担っていくのは皆さんが主体という考えを持っていただきたい」
=====
会場2
「まさに市民社会の創造なのだと思う。普通の人を探すのが難しいと言うけれど、それをあきらめていいのか。裁判員制度も始まる。あまりにも医療制度は偉い人だけで決められていないか」
鴨下
「がん対策基本法のがん対策基本計画を議論する協議会は患者団体の代表も含めて構成した。皆さん苦労して、自分たちの想いはあるけれど全体のことを考えて意見を取りまとめている。ある人が新しい民主主義の第一歩だと言ったけれど、ぜひこの動きに関心を持っていただきたい」
まだ質問の手は上がっていたが時間切れ。
最後に鈴木寛参院議員が講演した。
鈴木
「一市民としてこの運動に参加していきたいと考えている。私の専門は情報学、その中でも情報社会学とコミュニケーション教育なのだが、医療には現代社会の抱える問題が凝縮している。不条理なこと理不尽なことがいっぱいある。学者としては現場の問題点を抽出したいと思うし、立法者としては対策を取りたい。
我々は日々様々なトラブルに巻き込まれる。個人ではほとんど解決できないので社会や組織というものを作ってきた。ベースには倫理があるべきなのだが、ここ200年ほどは法律や社会制度のような規範で解決しようとしすぎている。これがひずみの原因。というのも法律は、責任者を定め権限と責務を与えるという構造を持っている。その責務がどんどん広くなっている。無過失責任とか結果責任という言葉に代表されるように故意でなくても責任を問われる。そうするとどうなるか。誰もが責任あり立場に就きたくない、責任を取りたくないということで社会が崩壊する。医療崩壊はまさにその象徴。
インターネットにベストエフォートという概念がある。インターネットが出てくるまでの通信は、NTTやKDDといった電気通信事業者が責任を持って回線を保証していた。しかしインターネットに運営者はいない。誰も保証はしないけれど、自発的につながって、それぞれの立場で最善を尽くすというもの。最初のころのインターネットはブチブチ切れた。でも誰も責任を取れとは言わなかった。そういうものだと皆が理解していたから。
医療の世界にもベストエフォートの概念を導入するべきでないか。誰が最善を尽くすのか。それは医療者だけではない。患者も家族もメディエーターも、それぞれがそれぞれにできる最善で関与する。
その世の中をどうやって作るのか。そのためには法律や制度の可能性と限界を理解する必要がある。
世の中で立場をわきまえて行動するようになると社会人になったと言われる。しかし現代社会では、良い社会人であることがかえって禍いを招く。立場をわきまえるから、組織の目的に従順になって、普通の人の立場から遊離していく。
ADRの話をすると法律のプロほど反発する。法律の限界を認めたくないというか、万能であると信じたいから。しかし、立場を超えて普通の人として良心のみに従って行動したら、そうはならないはず。
本当は我々が幸せになるために組織を作ったのに、組織によって人々が不幸にさせられているという逆転現象の起きるところまで来ている。ここで普通の人とは何かということになるけれど、一つの立場に拘泥しない様々な立場を内包した存在、自分がなったことのない立場のことも慮ることができる、そんな人のことだ。
もう一度医療について、政策のつくりかた、医療機関の運営の仕方、日々の診療現場考え直す必要がある。医師と患者の対立構造が一番不幸。一つひとつの現場で最善を尽くすにはどうすればよいのか。
必要なものは①関与する人間の能力と志と倫理②知恵や方法論、この二つがあったうえで初めて③社会制度・システム・法律が出てくる。それも①②に対してポジティブフィードバックをかけるという目的を達成してこそ意味がある。
現在の医療はあまりにも過剰な責任によって、ベストエフォートの芽が摘まれている。もう一度普通の人に戻って、良心に誓って、本当にその行動でよいのですかと自問する。資格や立場を超えて一人ひとりに戻ることが大切なんだと思う。
そういう人の連なりである現場が増えることが大切。そしてつながる。
一緒に知恵を出し、一緒に勇気を出して、一つひとつの現場を作り出そう。一緒にやっていこう。私も一市民として皆さんと一緒に活動していきたい」
今までモヤモヤしていたものが一気に具体的な像を結んだ気がする。ロハス・メディカルと私もその中に加わりたいと強く願う。
最後に和田所長が
「皆さん、それぞれの場へ持ち帰っていただき、一歩ずつ進んでいけたら」と総括して、幸せな日曜日の午後は幕を下ろした。












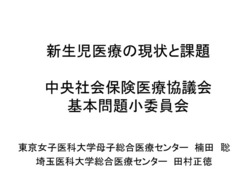
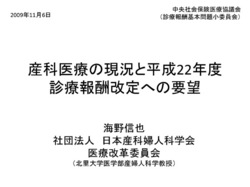

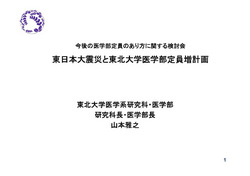


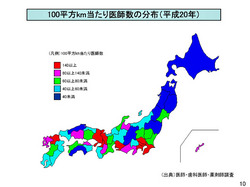
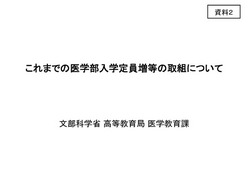
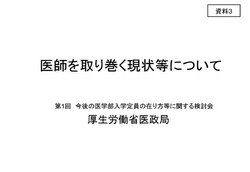






-thumb-250x170-4749.jpg)

























、大久保満男会長-thumb-250x194-4259.jpg)












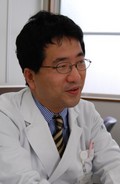












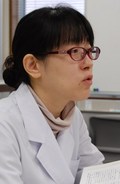








![IMG_9967[1].jpg](https://lohasmedical.jp/news/assets_c/2010/02/IMG_9967[1]-thumb-120x144-3915.jpg)











1106-thumb-250x167-3357.jpg)
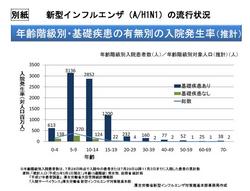












0918-thumb-250x170-3010.jpg)





0706-thumb-250x174-2370.jpg)



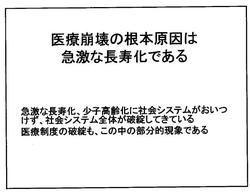


-thumb-250x170-1776.jpg)






